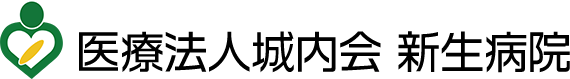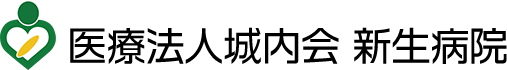形成外科とは
形成外科は何らかの理由によって体に生じた変形や欠損などを、さまざまな手法を駆使して、機能も含めて本来あるべき姿により近い状態に再建したり、整容的(みかけ、みばえ)によりきれいにすることを目的とした外科系の診療科です。
形成外科で治療を受けた方々が、笑顔で再び学校・社会生活に復帰してゆく姿を見ることが、形成外科専門医の最高の喜びです。
主な診療内容
形成外科で扱う疾患を(頻度が多いものを中心に)具体的にあげてみましょう。
(より詳しく知りたい方は日本形成外科学会の「形成外科で扱う疾患」ホームページをごらんください。)
- 熱傷(やけど)≫
- 外傷(切りキズ、すりキズ、圧挫創など)≫
- 顔面骨骨折(鼻骨骨折・頬骨骨折・眼窩(ブローアウト)骨折・上・下顎骨骨折)≫
- 母斑・色素斑(あざ・しみ)≫
- 血管腫(脈管奇形、血管奇形、リンパ管腫(リンパ管奇形)≫
- 皮膚・皮下(良性)腫瘍 (皮下のできもの)≫
- 皮膚(悪性)腫瘍(皮膚のできもの)≫
- 褥瘡・難治性潰瘍(床ずれ・糖尿病性・血管性・透析にともなうもの・膠原病などの慢性の皮膚潰瘍)≫
- 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド(もりあがった傷跡やそれによる突っ張り、ひきつり)≫
- 腋臭症(わきが)≫
- 陥入爪≫
- 眼瞼下垂(上まぶたが重い、視野がせまくなる)≫
- 先天異常(生まれつきの変形)≫
- 他科での手術の後の組織欠損(たとえば乳房再建など)≫
熱傷(やけど)
いわゆる”やけど”ですが、受傷の原因・部位・範囲・深さ・年齢などによって重傷度・治療法なども異なってきます。
例えば、「深さ」をとっても、日焼けなどのように、赤くなるだけで数日以内に軽快するもの(Ⅰ度熱傷といいます)から皮膚の全層やその下の組織までがダメージをうけた最も深いやけど(Ⅲ度熱傷といいます)までの4つの段階に分けられています(II度は浅いものと深いもの2種類)、またある一定以上の深さの熱傷では治った後も赤く、もり上がった跡(瘢痕、肥厚性瘢痕)が残る場合があります。
また、重傷度(決め方にはいくつかの方法があります)に関しても、通院だけで治療可能なものから、入院して全身管理が必要となるものまで、また保存的治療から手術を必要とするものまで、様々です。いずれにしても早期治療が重要です
外傷(切りキズ、すりキズ、圧挫創など)
皮膚の損傷に関しては、程度に応じて、つけかえなどの保存的に治療が可能なものから、デブリードマン(汚れた組織を除去する)・縫合などの処理が、さらには植皮(皮膚移植)、皮弁などの外科手術が必要なものまであります。
顔面骨骨折(鼻骨骨折・頬骨骨折・眼窩(ブローアウト)骨折・上・下顎骨骨折)
顔面骨骨折には、折れた場所によって鼻骨骨折・頬骨骨折・眼窩骨折(ブローアウト骨折)・上下顎骨骨折またはそれらが同時に起こったものなどに分類されます(同じ骨折でも折れ方によっていくつかの種類にわけられる場合 もあります)。骨折によっては、顔面の変形・知覚の異常・開口障害・複視(ものが二重にみえる)といった後遺障害が残るものもあり、新鮮期または二次的に手術が必要となる場合もあります。
母斑・色素斑(あざ・しみ)
いわゆる母斑とは生まれつきのあざ(赤あざ・黒あざ・青あざ等)のことで、色素斑は加齢に伴う皮膚の色素沈着です。一般的には、切除縫合、レーザーなどの治療になります。
血管腫(脈管奇形、血管奇形、リンパ管腫(リンパ管奇形)
いくつかの分類がありますが、ここでは次の5つについて解説します。
- 乳児血管腫(イチゴ状血管腫)
典型的には出産直後にはみられなかったのが生後間もなく赤い斑点ができ、盛り上がり始め数ヶ月で大きくなり、多くはイチゴのように赤く盛り上がった形状です。1才ころピークに達し、その後はゆっくり色が落ちていき、多くの場合小学校低学年くらいまでの間に赤みが引いてきます。
基本的には経過観察のみでよくなる、とされますが、最近では早期からプロプラノロールの内服治療や色素レーザー治療を行うことがあります。こうした治療を行うことによって、より早期に赤みが消えることが期待されます。
■ご案内 当院は「乳児血管腫診療施設」となりました。
(乳児血管腫診療施設紹介ページ)https://www.maruho.co.jp/clinicsearch/kekkanshu/nagasaki_shinseibyouin_L.html
- 毛細血管奇形(単純性血管腫)
うまれた時からある赤い平坦な「あざ」です。生まれつきの毛細血管の異常なので、厳密には血管腫ではなく、奇形に分類されます。毛細血管は動脈と静脈の間にあり、皮膚に広がる細くて薄い管ですが、それらが異常に増えて集まった状態です。自然に消えることはなく、ゆっくり色が濃くなったり大きくなったりすることがあります。大人になると盛り上がることがあります。
部位や大きさなどによって経過はさまざまですが、基本的にはゆっくりとした速さで病気が進んでいきます。治療としては、状況に応じてレーザー治療や、手術的な治療などが行われます。 - 静脈奇形(海綿状血管腫)
静脈奇形は、生まれつき静脈の成分が拡張・腫瘤化したもので、部位や大きさ、深さは様々です。体表面から青くすけてみえたり、手足の場合は下ろすとふくらむことが多く、石(静脈石)を触れることもあります。また、痛みをともなうことがあります。MRI、CTなどの画像検査を行って大きさや深さ、性状を検査します。
治療方法は部位や大きさによって異なりますが、MRIや超音波などの画像検査を行って最適な治療方法を検討します。治療方法としては手術や特殊な薬を病変の中に注入して小さくする硬化療法などがあります。 - 動静脈奇形
動静脈奇形は、動脈→毛細血管→静脈という血管の構造をとらず、動脈から静脈に抜けてしまい、血流の早い病変が形成されたものです。動脈の血圧が、静脈にかかるので、多くの病変は進行性です。皮膚の赤あざや拍動性の瘤からはじまり、大きくなると出血や痛みを伴うことがあり、血流が多くなると心臓に負担がかかってくることがあります。
小さな病変の場合には、手術的な切除を行うことが可能ですが、大きな病変でを切除をする場合は、出血や再増大の危険があり、前もって栄養血管を詰める塞栓療法などが必要になることがあります。
血管腫、血管奇形には様々な種類があり、治療方法もそれぞれ異なります。早い段階での治療のほうができるだけ目立たなく治すことが可能となります。なるべく早い段階で、血管腫・血管奇形の治療に習熟した医師の診察を仰ぐことをお勧めします。 - リンパ管腫(リンパ管奇形)
広い意味の血管奇形の一つですが、血管ではなくリンパ管に病気が起きています。リンパ管腫の多くは生まれつきの病気ですが、胎生期のリンパ管が形成される時期に何らかの異常があり生じると考えられていますが、原因はわかっていません。
首やわきの下にできることが多いですが、全身どこにでもできる可能性があります。かぜをひいたときなどに炎症(熱発と腫脹と痛み)を生じる時があります。おなかの中にできると外見では分かりにくいこともあります。
特に首にできた場合は、気道を圧迫し呼吸困難となり、呼吸管理などを要する重症管理が必要となることもあります。
リンパ管腫の中には特に症状を認めないものがある。そうした場合には定期的な経過観察のみで問題はありません。
なんらかの症状を認める場合には、治療方法としては手術により切除する、特殊な薬(ピシバニール、ブレオマイシン、高濃度アルコール、高濃度糖水、フィブリン糊等)を用いてリンパ管をつまらせる硬化療法、抗癌剤(ビンクリスチン等)、インターフェロン療法、ステロイド療法、レーザー焼灼法などが行われます。またリンパ液の喪失が多い場合には高カロリー輸液、中鎖脂肪酸食、高タンパク食など栄養療法も行う場合があります。
血管腫、血管奇形、リンパ管腫(リンパ管奇形)、脈管奇形には様々な種類があり、治療方法もそれぞれ異なります。
早い段階での治療のほうができるだけ目立たなく治すことが可能となります。
リンパ管腫(リンパ管奇形)では約80%は満足のいく結果(消失もしくは縮小して生活に支障をきたさない)を得られますが、一部には外観の問題、気道狭窄などの機能的問題を解決できず不自由な生活を余儀なくされているとの報告があります。なるべく早い段階で、血管腫・血管奇形の治療に習熟した医師の診察を仰ぐことをお勧めします。
皮膚・皮下(良性)腫瘍 (皮下のできもの)
一般に”ほくろ”と呼ばれるものの大部分はこれにあたります。他には粉瘤・脂肪腫・脂漏性角化症などが頻度の高い皮膚良性腫瘍です。
皮膚(悪性)腫瘍(皮膚のできもの)
皮膚の癌で、代表的なものに、悪性黒色腫・有棘細胞癌・基底細胞癌といったものがあります。
ある程度特徴的な外見・病態を示しますが、切除して細胞レベルで詳しく調べないと(病理組織検査といいます)はっきり分からない場合もあります。
悪性度も種類により異なります。基本的には、手術を中心とした治療がスタンダードとなり、腫瘍の種類によっては化学療法・放射線療法などを合わせた集学的治療が必要になります。
褥瘡・難治性潰瘍(床ずれ・糖尿病性・血管性・透析にともなうもの・膠原病などの慢性の皮膚潰瘍)
褥瘡(床ずれ)は、低栄養、体動制限、高度のるいそう、高度の肥満、などで引き起こされることがありますが、予防と管理が重要となります。除圧、創管理が発達しており、必要に応じて、手術、先端治療も適応となります。
糖尿病性足病変は増加中の疾患であり、足の知覚(感覚)の低下により、やけどや圧迫を受けても気がつかない事が多く、いったんキズつくと感染が進行しやすくなります。血管の狭窄(縮こまること)、血栓・塞栓(血管が詰まること)でも十分な血液が組織にみたされなくなります。更に、透析は、半数以上が糖尿病が原因であり、知覚が低下していること、感染しやすいこと、血管異常が起きやすい事から重症になりがちです。膠原病では全身性の組織の代謝障害があり、一端組織にキズがつくと修復・治癒が極めて困難となりがちです。
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド(もりあがった傷跡やそれによる突っ張り、ひきつり)
熱傷・外傷・ピアス・手術の傷跡・虫刺されなどが原因となり(原因不明の場合もあります)皮膚が赤く硬く盛り上がり、痒みを伴う疾患です(ときにそれが原因で皮膚がつっぱり動きが悪くなって
しまったりします)。
治療は、外科的なもの、保存的なもの(ステロイドの外用、注入など)、放射線照射など程度・部位等によってさまざまですが、「ケロイド」は治療に苦慮するケースも少なくありません。
腋臭症(わきが)
いわゆる「ワキガ」と呼ばれるものですが、当院では「剪除法」を用いて治療します。(保険診療)
陥入爪
足の指(特に母趾)の爪が変形して周囲の皮膚に突き刺さるようになり、痛いだけでなく、ときに発赤・感染・肉芽形成をきたす疾患です。ハイヒールを履く現代人の病気ともいわれています。重症度もさまざま(骨の変形をともなう場合もあります)で、それに合わせて治療も多くの方法(マチワイヤー、フェノール法、手術切除)があります。
眼瞼下垂(上まぶたが重い、視野がせまくなる)
先天的なもの・加齢によるもの・外的原因によるもの(白内障手術後、コンタクトレンズの装着)などがあります。特に多いのが加齢による眼瞼下垂です(保険診療)。上まぶたが垂れ下がって眼があがりづらい・まぶたが重苦しい・視野が狭くなる等の症状が現れます。
さらに、代償的に前頭筋(眉毛をあげることで眼をあけようとする)が過度に使われるため頭痛がしたり、頭が重かったりといった症状もでてくるようです。原因には、加齢による皮膚のたるみ、上眼瞼挙筋(まぶたを上げる筋肉)の機能低下、瞼板における上眼瞼挙筋の付着部の離脱等があり、それらを見極めてから治療(手術)をおこないます(保険診療)
先天異常(生まれつきの変形)
生まれつきの(外表性)変形
唇裂・口蓋裂
手足の奇形
他科での手術の後の組織欠損(たとえば乳房再建など)
他科(乳腺外科、耳鼻科、整形外科、消化器外科、放射線治療科など)とともに再建をおこないます。
形成外科の治療について
「形成外科とは」の項で述べましたように、形成外科の目標とするところは、単に病気を治すばかりではなく、いろいろな手技を駆使することで、形態・機能を回復し、生活の質(QOL; quality of life
)を向上させるところにあります。
形成外科でおこなう手技
● 縫合
● 植皮
● 皮弁
● ティッシュー・エキスパンダー
● マイクロサージャリー
● 頭蓋顎顔面骨延長
形成外科Q&A
Q:形成外科と美容外科ってどう違うの?
形成外科は外科系診療科の中の一専門分野であり、大別して二つの専門領域があります。 「再建外科」と「美容外科」です。組織の異常、変形や欠損などの「疾患」を治療対象とするのが「再建外科」であり、疾患とは言えないが、ご自身が大変気にしている微妙な形状を治療対象とするのが「美容外科」です。いずれも、<QOLの向上に貢献する>という点ではかわりませんが、医療法上は各々独立した標榜科になっています。
さらに分かりやすく言うと、「形成外科では見た目や機能の病的な異常を、手術などの治療で正常に近づけることが主な目標になります。一方美容外科では、病的でない正常な外観を更に改善するために手術を行います。手術方法はお互いによく似ていますが、その対象となる疾患も目的も少しづつ異なります。
しかし形成外科的な手術、具体的には交通事故の外傷、乳がん切除後の乳房の再建などの治療をする場合にも、そこにはやはり美容外科的な要素を要求されることが多いものなのです。そして美容手術の手技はそのほとんどで形成外科のテクニックが基礎になっています。つまりこの二つの外科領域は、お互いに持ちつ持たれつ、車の両輪のような関係にあるといえるのです(『?形成外科!』野崎敏彦)」
Q:整形外科と形成外科ってどこがちがうの?
整形外科は、手足の筋肉、骨・関節と脊椎(背骨)の病気・外傷を扱う専門家です。手の外傷などは、整形外科でも形成外科でも扱います。また、四肢体幹の骨の専門は整形外科ですが、顔面骨、顎の骨の外傷は、形成外科で治療しています